夏の草花から選ばれた、九つの日本の伝統色。
この場所ですごした夏の思い出を情緒豊かに彩ります。
筆が走るたび、時が刻まれ、色が生まれる。
これは、筆で紡ぐ、一刻一景の物語。
草花の息づかいを映したストロークが、画面いっぱいに舞い踊ります。
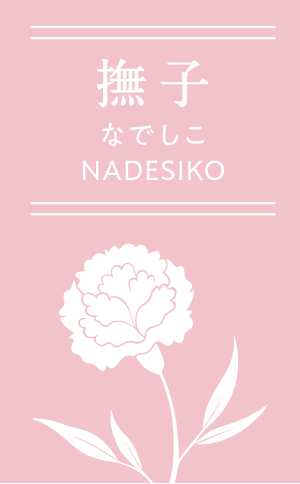
撫子(なでしこ)は、紫みを帯びた柔らかな薄紅色で、「撫子色」ともよばれます。夏から秋にかけて咲く撫子の花に由来し、やさしさと上品さを感じさせる桃色系統の色です。
この花は古くから日本人に親しまれてきました。『万葉集』や『源氏物語』などの古典文学にもたびたび登場し、四季の草花としての存在が詠まれています。撫子の仲間であるカワラナデシコは、秋の七草の一つに数えられ、細く裂けた花びらと可憐なたたずまいをもち、古来より愛されてきました。日本人特有の美しさをそなえる女性像を表す「大和撫子」は、このカワラナデシコの別名です。
撫子色は、平安時代の貴族社会においても衣服の襲(かさね)色目や染め色として用いられ、自然の季節感を表す色として高く評価されていました。涼やかさや儚さを感じさせるその色合いは、繊細な感性を重んじる日本文化のあり方を今に伝えています。
また、松尾芭蕉の『奥の細道』には、「かさねとは八重撫子の名なるべし」と詠まれています。「かさね」は少女の名であり、「撫でて可愛がった子」の意味が重ねられています。撫子の可憐な色と、幼い子の姿が結びつけられた表現です。
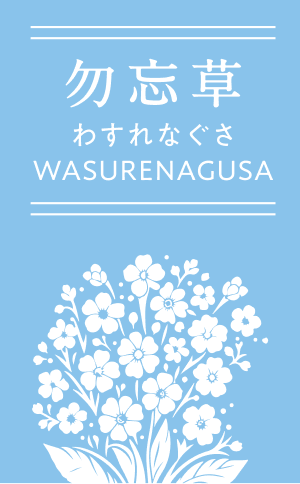
勿忘草(わすれなぐさ)は、初夏に小さな青い花を咲かせるヨーロッパ原産の多年草で、その花の色をさして「勿忘草色」と呼ばれます。やや紫みを帯びた明るい青で、鮮やかすぎず、落ち着きのある中間的な色調が特徴です。
ヨーロッパでは青い花が少なかったことから、この植物は特別な存在として人々に扱われてきました。名前の由来は、中世ドイツの伝説にあります。恋人のために川辺の青い花を摘もうとした青年が川に流され、「私を忘れないで」という言葉を残したという伝承から、花名としてForget me notがつけられたといわれています。
日本ではこの伝承をもとに、明治時代に植物学者の川上滝弥が「勿忘草」と訳しました。以後その名が広まり、現在に至ります。
また「勿忘草色」という色名も明治以降に日本に定着しました。婦人雑誌や染色見本帳などで紹介され、西洋の文化とともに広がる中で、控えめで清涼感のある近代的な色として受け入れられた、比較的新しい色です。
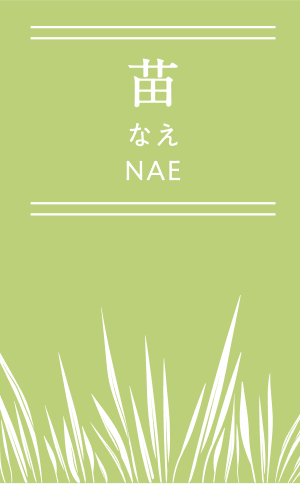
苗色(なえいろ)は、夏の田に育つ稲の若苗のような、やや黄みを帯びた穏やかな緑色を指します。初夏の稲の色である明るい若苗色とは異なり、陽光と水に育まれて葉に深みが出る頃の色を表しています。夏にかけて広がる水田の緑をそのまま写し取ったような色であり、季節の移ろいを感じさせます。
この色名は、平安時代末期の有職故実書『助無智秘抄(じょむちひしょう)』に「苗色トハ黄気アル青物也」と記されており、当時すでに季節に応じた色彩のひとつとして認識されていたことがうかがえます。苗色は襲(かさね)色目においても夏の配色に用いられ、自然の色を取り入れた装束の中に位置づけられていました。
表地と裏地を異なる色で重ねることで生まれる繊細な色の調和が重視された平安貴族の装束では、苗色のように控えめながらも明確な季節感を持つ色が重宝されたのです。天皇の側で仕える人々の服色にも用いられていたという説もあります。
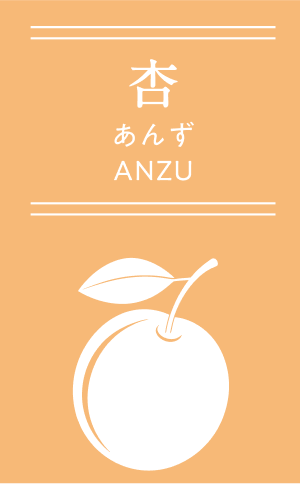
杏色(あんずいろ)は、やや赤みを帯びた淡いオレンジ色で、夏に旬をむかえる杏の熟した実に由来します。黄色と赤の中間にあたる穏やかな色調であり、強い日差しの下でも目にやさしい印象を保ちます。
杏は中国原産の果樹で、日本には奈良時代以前に伝来したとされます。平安時代の『古今和歌集』には、杏を意味する「唐桃(からもも)」にかかわる表現が見られます。その中に「あふからも ものはなほこそ かなしけれ わかれけむことを かねて思へば」という一首がありますが、これは「別れることを考えると、会っている時からもう悲しい」といった意味です。ここで詠まれた「あふからも」は「会ってもすぐに」の意とともに、「唐桃(杏)」を掛けた語とされ、果実の名が情感を盛り立てるモチーフとして扱われていたことがうかがえます。
一方、色名としての「杏色」が使われるようになったのは近代に入ってからです。明治から大正期にかけての染織見本帳や婦人雑誌にその名前が登場するようになり、植物や果実にちなんだ新たな色名のひとつとして定着していきました。杏を使用したジャムやお菓子が一般的になった現在では、日常生活にお馴染みの色だといえるでしょう。
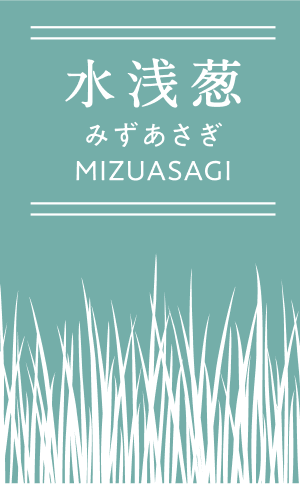
水浅葱(みずあさぎ)は、藍染の淡い色で、明るい青緑色です。この色は、夏の衣服に視覚的な涼しさを与えるため、古くから重用されてきました。水浅葱の青みを少し濃くした色を「浅葱」といい、これも江戸時代以降、武士の羽織や裃(かみしも)などにも多く用いられてきた伝統色です。水浅葱はその発色を薄くしたもので、江戸時代の染色技法や色名の中にすでに見られます。
藍染においては、「藍色四十八色」と呼ばれるように、染めの回数や時間に応じて多様な色名が存在します。藍の染液に最も短時間浸した、白に近い色を「白藍(しらあい)」、そこからわずかに染めを重ねた薄い水色を「甕覗(かめのぞき)」と呼びます。この「甕覗」にさらにわずかに染めを加え、やや青みが増した水色が「水浅葱」です。いずれも藍染の初期段階で得られる淡色であり、染液にひたす時間や濃度の調整によって段階的に色が深まっていきます。
このように藍染の過程から生まれる色である水浅葱は、素材によっても印象が変わります。とくに絹や麻に染めると、その光沢や風通しの良さとあいまって、色の爽やかさが際立ちます。通気性と見た目の軽さが求められる夏の衣料において、こうした淡い藍色は実用性と調和を備えた色として重宝されてきました。

露草(つゆくさ)は、夏の朝に青い花を咲かせる一年草であり、その花の色を指して「露草色」と呼ばれます。やや紫みを帯びた明るい青で、透明感があり、湿度の高い日本の夏においては視覚的な涼しさを与える色調です。開花期は6月から9月にかけてであり、夏の自然を彩る草花のひとつとされています。
露草の青は、「コンメリニン」と呼ばれる水溶性の色素によって生まれます。この色素は水に極めて溶けやすいため、色が定着しにくいという特徴があります。そのため染色材料として広く用いられることはありませんが、一時的な下絵や仮染めに利用されてきました。古くは平安時代から、露草の汁で紙に下絵を描き、その上から墨で本描きをする技法がありました。
色がすぐに流れ落ちてしまうという性質から、露草は古典文学において象徴的な意味を持つようになります。「つゆくさの」は枕詞として使われ、うつろう、消える、といった語にかかる表現となりました。
そのような背景もあり、露草色は、その明るく清らかな印象とともに、儚いイメージも備えており、日本の夏の情景の中に涼感をもたらす存在です。
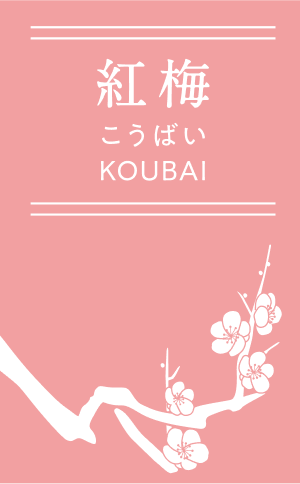
紅梅(こうばい)は、梅の花の中でも紅色の花に由来する色名で、やや紫みを帯びた赤系統の伝統色です。平安時代にはすでに色名として用いられており、当時の染色技術の中でも代表的な紅系の色のひとつとされていました。紅梅色はその濃度によって分類され、「濃紅梅(こきこうばい)」、「中紅梅(なかこうばい)」、「淡紅梅(うすこうばい)」の三種に分けられます。それぞれ異なる季節や用途に応じて使い分けられ、衣服の色目に取り入れられてきました。
平安時代の貴族文化においては、四季の変化に合わせた「襲(かさね)の色目」が重視され、衣の表裏の色を組み合わせて季節感を表現しました。その中でも夏の色目として知られる「杜若(かきつばた)」は、表に淡萌黄(うすもえぎ)、裏に淡紅梅を配したものです。これは、初夏の若葉の瑞々しさと、紅梅の残り香のようなやわらかな紅色を重ねることで、季節の移り変わりを表現したものです。また、赤系統である薄紅梅は、緑系統の淡萌黄を引き立て、夏らしさを穏やかに演出します。
紅梅系の布地は主に紅花(べにばな)で染められますが、その染色には高度で繊細な技術が求められます。季節や素材、文化とともに育まれた紅梅は、日本の染色文化を象徴する色のひとつといえるでしょう。
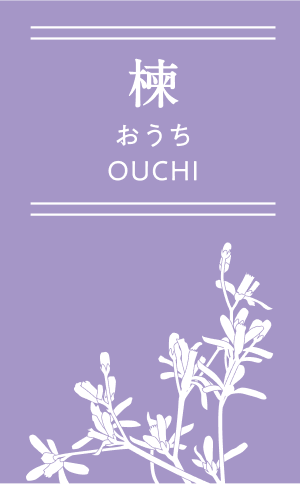
楝(おうち)は、灰色がかった淡い紫色を指し、初夏に咲く楝の花の色に由来します。楝はセンダン科の落葉高木で、一般には「センダン」と呼ばれます。楝はセンダンの古名であり、春の終わりから初夏にかけて、枝先に小さな淡紫色の花を多数咲かせるのが特徴です。葉は羽状複葉で、秋には黄葉し、冬には実を残して落葉します。
『枕草子』には、「木のさまにくげなれど 楝の花 いとおかし」と記されています。直訳すれば、「木の姿は粗野な様子であるけれども、楝の花はとても趣がある」となり、花の持つ静かな美しさが古くから認識されていたことがうかがえます。『万葉集』をはじめ、『源氏物語』や和歌の中にも楝の名はたびたび登場し、その風姿や開花の季節感を通して、文学的にも親しまれてきました。
楝色は視覚的な重さが少なく、涼感を与えるため、夏の装束や調度の色としても用いられてきました。襲(かさね)色目では、淡緑や白などと組み合わせ、上品な配色を構成するための一色とされています。
このように楝色は、花の咲く季節や木の姿とともに記憶されてきた色であり、夏の到来と結びつく伝統色のひとつです。
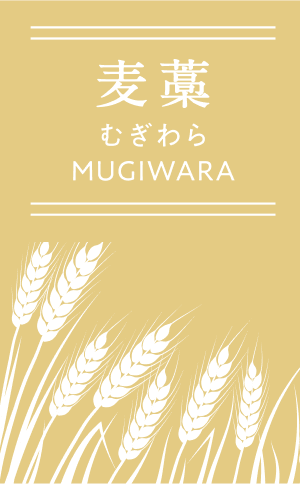
麦藁(むぎわら)は、収穫期を迎えた麦の茎の色に由来する、淡くややくすんだ黄色を指す色名です。麦の収穫は初夏から盛夏にかけて行われ、麦藁色もまた、その季節特有の光景を反映した色として定着しています。新緑や若草色とは異なり、緑みを含まない乾いた黄味を帯びている点が特徴です。
色彩としては明るく、かつ穏やかな色調を持つため、夏の装いにも取り入れやすい色とされてきました。日差しを反射しやすい特性を活かし、盛夏の衣服や帽子、和装小物などに用いられることも多いです。とくに麻や綿といった通気性に富んだ素材と相性がよく、見た目の涼やかさと実用性を兼ね備えた色といえます。
麦藁色という名称が文献に登場するのは比較的新しい時代で、明治から昭和初期にかけて編集された染色見本帳や色名事典の中にその名を見ることができます。近代以降、自然に由来する色名が整理される中で、麦藁色も農耕と季節の関係を表す色のひとつとして分類されていきました。また、現在では白ワインの色を表現する際にも使われ、日常のさまざまな場面で見聞きされる機会が増えています。
このように麦藁色は、夏の農村風景や農作業に関わる色彩のひとつとして位置づけられ、実用と季節感の両面から用いられてきた伝統色です。





